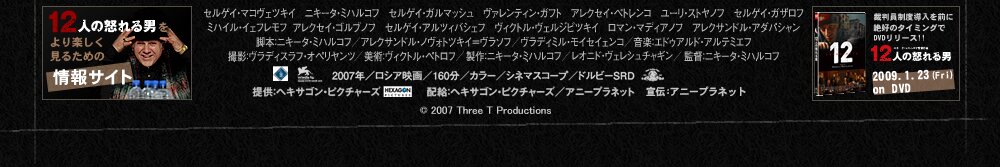ロシアのとある裁判所で、センセーショナルな殺人事件に結論を下す瞬間が近づいていた。被告人はチェチェンの少年、ロシア軍将校だった養父を殺害した罪で第一級殺人の罪に問われていた。検察は最高刑を求刑。有罪となれば一生、刑務所に拘束される運命だ。3日間にわたる審議も終了し、市民から選ばれた12人の陪審員による評決を待つばかりとなった。
彼らは改装中の陪審員室代わりに指定された学校の体育館に通されて、全員一致の評決が出るまでの間、携帯電話を没収されて幽閉される。バスケットボールのゴールや格子の嵌められたピアノといった備品に囲まれた陪審員たち。冷静にことを進めようとする男に促されて、12人の男たちは評決を下すためにテーブルを囲んだ。審議中に聞いた隣人たちによる証言、現場に残された証拠品、さらには午後の予定が差し迫っている男たちの思惑もあって、当初は短時間の話し合いで有罪の結論が出ると思われた。 乱暴なチェチェンの少年が世話になったロシア人の養父を惨殺した――そのような図式で簡単に断罪しようとする空気があり、挙手による投票で、ほぼ有罪の結論に至ると思いきや、陪審員1番がおずおずと有罪に同意できないと言い出した。
陪審員1番は自信なさげに結論を出すには早すぎるのではないかと疑問を呈し、手を挙げて終わりでいいのかと、男たちに問いただした。話し合うために、再度投票を行おうと提案。その結果、無実を主張するのが自分ひとりであったなら有罪に同意をすると言いだした。無記名での投票の結果、無実票が2票に増える。新たに無実票を投じたのは、穏やかな表情を浮かべる陪審員4番だった。ユダヤ人特有の美徳と思慮深さで考え直したと前置きし、裁判中の弁護士に疑問が湧いたと語る。被告についた弁護士にやる気がなかったと主張した。この“転向”をきっかけに、陪審員たちは事件を吟味するなかで、次々と自分の過去や経験を語りだし、裁判にのめりこんでいく…。